BooT.oneとは何者か? のその前に、Revitを知る
- 2024.11.25

BooT.oneとは何者か? のその前に、Revitを知る
Revitを使われたことのあるか方なら1度は耳にしたことがある(と思いたい)BooT.oneとは果たして何者なのか? をお伝えする前にまずそのベースとなるRevitに関してお伝えしておきます。
この情報は、何の役にも立たない情報なので、軽く読み飛ばしていただければと思います。
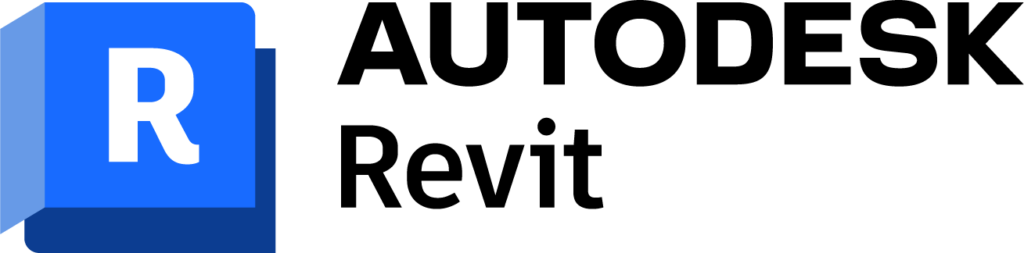
Revitを知る
Revitをお使いの方が最初に直面する問題が、「どうすればモデリングできるの?」ではないでしょうか? 他社のツールだと、なんとなくモデルを作れた! うれしい! 楽しい! お、3次元!!となるのに、なぜか Revitは????から始まってしまう。2次元作図をしていた時のように 平面図なら通り芯を描きたい。 立面図なら階高をセットしたい。敷地を書きたい。壁の線を入れたい。etc. と思ってもなぜか思い通りにならない。作図を意図せず3次元モデルを作れるんだよね、と思って取り組んでもなぜか思ったようにならない。この最初の印象が悪いことが、建築の中でもどちらかというとデザイナーの担当者に不評なのが多分Revitではないでしょうか?
ですが筆者はデザイナー系ではないので、この辺りをたいして問題と思っていません。なぜ使いづらいと思われるツールそのものが問題にならないのか。そこにRevitが世界中で使われている最大の要因があるのだと思っています。
Revitは、意匠・構造・設備を対象に
Revitの歴史を紐解くと、Pro-Engineerに所属していた開発者が建築系のパラメトリックモデリングプラットフォームが不足していると認識して会社設立に動いたのが1997年だそうです。すでに存在していたヨーロッパ某社の製品を見て、これは自分たちの求めるものではないと判断したこともあり、建築3次元CADの開発をスタートしたとされています。製造系では出来ていたことを建築系に持ち込むというアイデアは、業界を研究したからできたことだったのか、技術力と信念がなせる技だったのかはわかりませんし、何が自分たちの求めるものではないと判断したのかの詳細も分かりません。ただ、建築分野にパラメトリックモデリングプラットフォームが必要であると判断したことは間違いないようですし、先行していたツールにケチをつけるぐらいの信念はあったのだと思います。
正直、よくこんな複雑なプラットフォームを考えつくものだと今でもうなるしかないのは、筆者の無知がなせる振る舞いでしょうか?
2000年に最初のリリースをして2002年にはAutodeskに買収されているので、Autodeskもしたたかではありますが、意外とアプローチは早かったようで、何度も買収を断られたとの情報もあります。その後2005年にはRevit Structureを発表、さらに2006年にはMEP版(当時はSystemsと命名されています)が紹介されており、2008年には Revit Architecture 2008、Revit Structure 2008、Revit MEP 2008として意匠・構造・設備用のRevitがそろい踏みで販売されています。この建築設計者の3大業種に統一プラットフォームを提供するという方針は、1つのオリジナルファイルフォーマットで連携することの優位性とともに、非常に興味深かったことを記憶しています。そして筆者が「「使いづらい」が問題ではない」と冒頭に書いたのもこの辺りに端を発しています。
構造の場合、ただ構造の3次元モデリングを行うツールということであれば、感動もなかったと思うのですが、構造部材のモデリングだけではなく、接合部の境界条件、荷重、荷重セットなどにも対応できていて、構造解析と構造設計、さらには意匠設計との連携がイメージできたときに、構造設計を少しだけかじったことのある筆者には、期待を感じさせてくれたことに間違いはありません。と言っても、国ごとの仕様やルールが、その理想を微妙に阻むのはよくある話しですが。
MEPも空調部分では意匠設計による部屋という空間と断熱性能などの情報とともに、部屋に必要な熱量を計算してくれて、簡易配管ルートの設定提案まで行ってくれるという流れは、これも3次元パラメトリックプラットフォームの恩恵と妙に納得した記憶があります。電気の容量集計もしかり。設備の専門家ではなかったのですが、この機能によって設備設計者はこのように形で設計を行っているのかと、アプリケーションから逆に学ぶきっかけにもなったことを覚えています。
ただ、全員が同じプラットフォームを使うことが理想であることに対しての最大の抵抗は、導入コストだったと思います。2010年ごろの価格はArchitecture、Structure、Mepが各90万円程度。今のように統合されていなくて別々に販売されていました
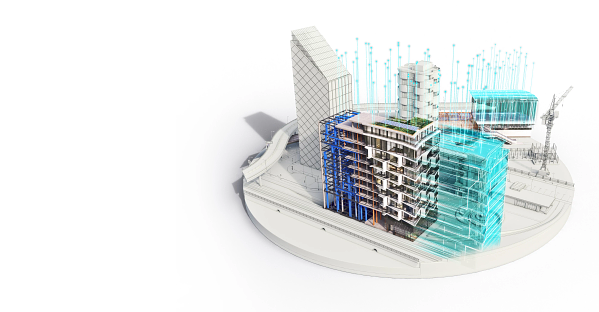
独白
Revitが、現在も意匠・構造・設備に対応した機能を持っていることは皆さんもご承知の通りだと思います。開発当初の熱い思いは長い年月の間に薄れていることがあるかもしれません。また、開発開始から25年以上を経過し、世の中の技術環境も変化しています。建築業界がBIMというコンセプトを失うことはないと思いますが、デジタルな環境が私たちの生活環境をより豊かにしてくれることを期待しつつ、BIMの過去と現在を取り混ぜてブログをしていきたいと思います。
